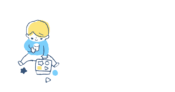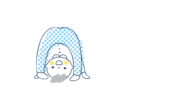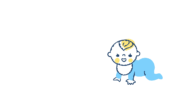報われないお母さん親衛隊
この話は、多くの人にわかってもらえるようなものではなく、ニッチな層にだけグサッと刺さるであろうお話です。
わたしと同じような気持ちになっていた人がきっとこの世のどこかにいるはずで、その人たちに届けばいいなと思って書いてみます。
お父さんが苦手だった
わたしはずっと父が苦手だった。
仕事ばっかりしてて、家事も育児も母に任せきり。
たまに家にいても、野球かゴルフのテレビばっかり観ている。
お酒くさいしタバコくさいしおじさん臭い。
洗面所でオエッてやるのも、わたしの彼氏がどんな人か根掘り葉掘り聞いてくるデリカシーのなさも、ぜんぶだいっきらいだった。
ひとりで家事育児全部担って、いつもてんてこ舞いの母が気の毒でたまらなかった。
「お母さん、なんでこんな人と結婚したんだろう」
いつも本気でそう思っていた。というか口に出して言っていた。
その一方で、ぶつくさ文句は言っても、なんだかんだ尽くしている母にもジリジリしていた。
「まったく。お父さんたらいやになっちゃう」なんて言いながら、父の身の回りの世話を何から何までやって、毎朝玄関で父にアイロンのかかったハンカチと靴べらを差し出す甲斐甲斐しい姿を見ては、「そんなことしなくていいのに」とうんざりしていた。
今思えば、母は典型的なケアテイカーで、「家族に尽くしている自分」でいる必要があったのだから、わたしがいくら言ったところで、やめるはずなどないのだ。
お母さんがかわいそう
母がケアテイカーだなんて知る由もない当時のわたしは、中学生くらいになると、母の代わりに母が言いたいであろうことを、ぜんぶ代弁して父にぶつけていた。
「なんでそんなにえらそうなの?」
「お父さんも少しは動きなよ。」
「お金稼いでればいいってもんじゃないからね。」
「お母さんがかわいそうじゃん!」
今思えば、父から見たわたしは、相当小生意気な娘だったと思う。
しかも言ってることがそこそこ正論なだけに、余計に腹が立ったことだろう。
そうしてわたしと父はいつもぶつかっていた。
似たもの同士の屈辱
もちろん、父とぶつかるのも楽ではなかったけれど、そんなことより何よりしんどかったのは、父に歯向かうわたしを見て、母や兄に「父と似たもの同士」と言われることだった。
ふたりは「ようこは結局お父さん似だからなぁ」と言って、結託したようにニタニタ笑った。
そのことが他の何より屈辱的で耐えがたいことだった。
わたしとしては、お母さんがあんまり気の毒だから、自分が盾になるような気持で父に歯向かっていたのに、その後ろで守られているハズの母からは、「もういい加減にしなさいよ」と諫められたり、「そんなにムキになってばかみたい」と呆れられたりするだけで、感謝されることは一度もなかった。
(実際、わたしが父に歯向かえば、家の中は険悪になるし、母は助かるどころか迷惑してたいたと思う。)
母が大好きで、大好きな母に好かれたくてやってるこの行為を、母はよろこぶどころか呆れて見ている。
母の一味に入りたくてやってるのに、逆にどんどん父に近づいてしまって、何も言わない他の兄弟がどんどん母に近づいているように感じる。
当時はこんな風にうまく言語化できなかったけれど、あのどうしようもない焦りは、煮えたぎるような悔しさは、つまりはそういうことだったのだ。
似た者同士と笑われた場面を思い出しただけで、奥歯がギリギリする。
報われないお母さん親衛隊
今ならわかる。
わたしが、父に向けていた怒りは、母にわかってもらえない悔しさだ。
かわいそうな母を、父という仮想敵から守ることで、母はわたしを必要とし愛してくれる。
「ようこがいてくれて助かった」と言って、しあわせそうに笑う母の顔が見たかった。
そういう脳内ストーリーを勝手に作り上げて、頼まれてもないのに勝手に「お母さん親衛隊」に立候補して、父という仮想敵を必死で攻撃していた。
でも、わたしが描いたシナリオ通りの展開にはならず、むしろ逆効果になっていく。
どうしてわかってくれないの!
わたしはお母さんのいちばんになりたいんだよ!
きっとずっとそう言いたかった。
あのときのわたしは、母にわかってもらえない悔しさの取り扱いに困って、常にイライラして周りに当たり散らしていた。
万年反抗期と言われていたわたしの怒りの源泉はここにある。
お母さん親衛隊をやめた日
おとなになってもしばらくはお母さん親衛隊のままだった。
父のことはもちろん、母を困らせる人を片っ端から非難して、母の護衛をしていた。
それだけじゃなくて、職場など母とは関係ないところでも、父や周りの人に似たタイプの人を見つけては、正義感を振りかざして敵対していた。
気づけば、常に周りに仮想敵を探してイライラしてるばかりの、めんどくさいやつになっていた。
当時は、どうしてこんなに人にイライラするのか自分でもわからなかった。
当然、どこにいっても人間関係で苦労した。
でも、心理学やインナーチャイルドとの出会いがわたしを変えてくれた。
心の仕組みを知って、それまで父や周りの人たちに向けていた怒りは、母にわかってもらえない悔しさだということに気づき、あの頃の自分の痛みを深く理解したとき、ふっと力が抜けたようだった。
もういいや。
無理な諦めとかじゃなくて、本当にそう思えたら、仮想敵は必要なくなった。世界はだんだん優しくなった。
報われないお母さん親衛隊だった痛みを、今のわたしならわかってあげられるし、今のわたしなら癒してあげられる。
本当は、父のことも母のことも大好きで、ただただ愛されたかっただけの幼いわたし。
自分で自分のいちばんの理解者になることができると、お母さん親衛隊はやめられる。
それにしても、お父さんごめんね。